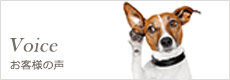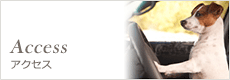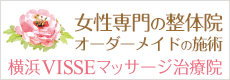月別 アーカイブ
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (24)
- 2025年2月 (23)
- 2025年1月 (24)
- 2024年12月 (26)
- 2024年11月 (28)
- 2024年10月 (30)
- 2024年9月 (28)
- 2024年8月 (19)
- 2024年7月 (27)
- 2024年6月 (28)
- 2024年5月 (26)
- 2024年4月 (21)
- 2024年3月 (26)
- 2024年2月 (24)
- 2024年1月 (21)
- 2023年12月 (24)
- 2023年11月 (24)
- 2023年10月 (23)
- 2023年9月 (23)
- 2023年8月 (17)
- 2023年7月 (26)
- 2023年6月 (14)
- 2023年5月 (22)
- 2023年4月 (26)
- 2023年3月 (24)
- 2023年2月 (26)
- 2023年1月 (19)
- 2022年12月 (23)
- 2022年11月 (22)
- 2022年10月 (21)
- 2022年9月 (15)
- 2022年8月 (18)
- 2022年7月 (23)
- 2022年6月 (26)
- 2022年5月 (21)
- 2022年4月 (18)
- 2022年3月 (25)
- 2022年2月 (22)
- 2022年1月 (20)
- 2021年12月 (26)
- 2021年11月 (27)
- 2021年10月 (23)
- 2021年9月 (20)
- 2021年8月 (13)
- 2021年7月 (20)
- 2021年6月 (20)
- 2021年5月 (19)
- 2021年4月 (25)
- 2021年3月 (27)
- 2021年2月 (21)
- 2021年1月 (19)
- 2020年12月 (23)
- 2020年11月 (28)
- 2020年10月 (22)
- 2020年9月 (18)
- 2020年8月 (20)
- 2020年7月 (25)
- 2020年6月 (24)
- 2020年5月 (18)
- 2020年4月 (19)
- 2020年3月 (21)
- 2020年2月 (18)
- 2020年1月 (16)
- 2019年12月 (25)
- 2019年11月 (21)
- 2019年10月 (25)
- 2019年9月 (24)
- 2019年8月 (16)
- 2019年7月 (26)
- 2019年6月 (29)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (14)
- 2019年3月 (20)
- 2019年2月 (16)
- 2019年1月 (15)
- 2018年12月 (15)
- 2018年11月 (18)
- 2018年10月 (17)
- 2018年9月 (17)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (18)
- 2018年6月 (15)
- 2018年5月 (15)
- 2018年4月 (20)
- 2018年3月 (22)
- 2018年2月 (15)
- 2018年1月 (16)
- 2017年12月 (18)
- 2017年11月 (18)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (21)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (17)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (12)
- 2017年4月 (16)
- 2017年3月 (16)
- 2017年2月 (10)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (14)
- 2016年11月 (12)
- 2016年10月 (12)
- 2016年9月 (12)
- 2016年8月 (12)
- 2016年7月 (13)
- 2016年6月 (18)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (19)
- 2016年3月 (13)
- 2016年2月 (15)
- 2016年1月 (16)
- 2015年12月 (16)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (14)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (13)
- 2015年6月 (15)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (23)
- 2015年3月 (15)
- 2015年2月 (15)
- 2015年1月 (13)
- 2014年12月 (12)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (18)
- 2014年8月 (9)
- 2014年7月 (12)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (12)
- 2014年4月 (16)
- 2014年3月 (12)
- 2014年2月 (8)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (8)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (6)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (6)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (1)
- 2012年2月 (1)
- 2012年1月 (1)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (1)
- 2011年7月 (1)
- 2011年5月 (2)
- 2011年4月 (1)
- 2011年1月 (2)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (2)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (1)
- 2010年7月 (4)
- 2010年6月 (2)
- 2010年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > Visse's Blog > アーカイブ > エッセイの最近のブログ記事
Visse's Blog エッセイの最近のブログ記事
横浜市の犬のしつけレッスン/お散歩の意味~ヴィッセのテキストから~
みなさんは「犬の生きがいって何だろう?」と考えたことはありますか?
犬は「好奇心」のかたまりです。その好奇心の先にあるものは「達成感」です。
そして、狩猟動物である犬の好奇心は、「探索する」「追いかける」「破壊する」
という行動によって満たされます。
ボールを追いかけるのは、獲物を追いかける本能であり、ぬいぐるみの綿を取り出して
破壊するのは、仕留めた動物の内臓を引っ張り出す本能です。
警察犬や災害救助犬、麻薬探知犬たちが生き生きとして仕事をするのも、
「探索行動」の探し当てた時の達成感から得られる自分自身の喜びと、
同時に飼い主の喜ぶ姿が犬にとっても幸せだからです。
僕が小学生の頃、友達と探検ごっこをして硬式野球のボールを見つけた時の
興奮は今でも忘れることができません。人も犬も何かを達成することで、
喜びを得られるように神様がインプットしています。
では、使役犬と違い仕事を持たない無職の家庭犬にとって、幸せとは何でしょうか?
それは、大好きな飼い主とのお散歩です。犬にとって大好きな飼い主と共に行動する
散歩の時間は、1日のうちで最も楽しい時間なのです。
散歩に行くことで外の世界と繋がり、五感が刺激され心と体を育むことができるのです。
毎日お散歩に行く犬の表情は、生き生きとしています。逆に散歩をしない子は、
外での刺激が不足し、神経質で臆病な子に育ちやすくなります。
とくに、長時間のお留守番をさせられて散歩が不足している犬の精神状態は、ストレスと不安を抱え
イライラしています。それが、無駄吠えや分離不安、噛みつきという行動に現れるのです。
問題行動の多くは、長時間のお留守番と散歩不足によるストレスなのです。
私の生徒さんでペットショップの店員さんや獣医さんに、
「お散歩は毎日行かなくても、飼い主の都合で行けば大丈夫ですよ」と言われた方が
何十人もいます。言われた方のほとんどが、小型犬の飼い主の方々ですが、
これは多分、犬を「家畜」として「飼う」ことを前提に言われているのか、
「お散歩」と「運動」の違いを理解できていないかのどちらかだと思います。
家畜ということであれば、お散歩は飼い主の都合で行きたい時に行こうが、
ケージに閉じ込めて、お留守番を長時間させようが理解できます。
しかし、「家族」として「共に暮らす」のであれば、豊かな生活環境を与え、
愛犬の心と体を健全に育むことが飼い主としての義務であり、責任ではないでしょうか?
その一番の義務と責任がお散歩だと私は思っています。
散歩は、愛犬の心と体を健全に育み、飼い主と信頼関係を築く基礎作りです。
散歩は、犬が犬としての喜びを感じる、1日で一番大切な時間なのです。
ヴィッセが考える犬のしつけとは、毎日のお散歩が土台としてあって成り立つと考えています。
【犬の行動欲求~狩猟動物としての本能を満たす~】
匂いを嗅ぐ、走る、追いかける、引っ張りっこ、破壊するetc. ⇒とくに、走らせて疲れさせることが重要。
※「疲れている犬は、良い犬だ」 ☜ イギリスの諺
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月11日 10:40





ストレスについて~ヴィッセのテキストから~
■ストレスとストレッサー
多くの方が「ストレスが多い」「ストレスになる」などという言い方をしていますが、
私たちが使う「ストレス」という言葉は、しばしば「ストレッサー」という言葉と混同して使われています。
●ストレス
なんらかの刺激によって心身に生じるゆがみ
●ストレッサー
ゆがみの原因となる刺激
つまり、ストレスの元となる事象は、厳密には「ストレッサー」ということになり、
それによって生じる心身の不調が「ストレス」なのです。
この世の中にはたくさんのストレッサーがあり、それをすべて避ける手段はありません。
本来、人(犬)の体には、ストレッサーに対する防御機能があり、
心身が参ってしまわないように働きかけを行ってはいますが、以下のように、それが敵わない場合、
- ストレッサーが強すぎる場合
- ストレスが長く続く場合
- 体調不良など、ストレッサーに対する防御力が落ちている場合
などは、心身にさまざまな不調が現れることになります。
人のストレスの元と言えば、一番多いのが職場での人間関係でしょう。犬の場合はと言うと、
他人との接触が人ほど多くないので、飼い主との関係性や家族間の関係性がストレスになります。
(主従関係を強要する、夫婦仲が悪い、小さな子供が乱暴に犬を扱うなど。)
また、生活環境が人間に比べてはるかに狭いので、人ほどのストレスは起こりにくいです。
そのストレスの原因となるストレッサーには、以下のように、実にさまざまなものがあります。
※人は5つのストレッサーがあるが、犬は赤字の3つ。
・物理的ストレッサー
天候、温度、気圧の変化など、「自然」によるもの
・社会的ストレッサー
仕事、家庭、経済状況の変化、人間関係など、社会環境によるもの
・環境的ストレッサー
騒音、振動、空気の汚れなど、外部環境によるもの
・身体的ストレッサー
病気、怪我、疲労、不眠など、体の変化によるもの
・精神的ストレッサー
怒り、悲しみ、葛藤、緊張、不安、悩み、寂しさなど、気持ちの変化によるもの
また、物理的・環境的・社会的ストレッサーは「外的ストレッサー」
身体的・精神的ストレッサーは「内的ストレッサー」と、区分けすることもできます。
人とのつながりや仕事などによるストレッサーだけではなく、暑さや寒さ、気圧の変化など、
些細な不快感や違和感、時には自覚がない外的刺激さえもストレッサーになることがあるのです。
犬の場合はというと、過去も未来もなくその一瞬一瞬を生きているので、たとえ嫌なことがあったとしても、
人のように引きずることはありませんし、適切な生活環境で暮らしていれば、ストレスが溜まることはありません。
ただ、長時間の留守番や、散歩不足の犬の場合は、ストレスアウトができず過度のストレスがかかると、
無駄吠えや飼い主を咬むなどの問題行動に発展していく場合があります。
また、お散歩レッスンでは、公園まで一切道草をさせないので、初めてレッスンを受けられた方から
「犬は匂いを嗅がせて歩かせないと、ストレスが溜まりませんか?」と聞かれたことがありますが、
これがストレスの使い方が間違っている例です。
飼い主の方には、公園に着いてから好きなだけ匂いを嗅がせれば、ストレスが溜まることはありませんし、
これを「メリハリ」と言います。と答えています。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月 3日 16:55





生者必滅会者定離
生ある者は必ず死に、出会った者は必ず別れるのがこの世の定めである。 という意味です。
かかりつけの動物病院の先生から、教えて頂いた言葉です。
また、聖書には、
「天の下では、何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。
生まれるのに時があり、死ぬにも時がある。」という節があります。
昨日、16年間一緒に暮らした猫のタロウが亡くなりました。
突然の別れでした。まだ心の整理がつきません。
これまでに、犬の大治郎(享年10才半)、猫のさくら(享年20才)、猫のももこ(享年20才)を
見送ってきましたが、かけがえのない存在との別れは、本当につらいものです。
いつか別れが来ると分かってはいても、ずっと一緒にいたいと思うのは、人間のエゴかも知れませんね。
そんな時に、この二つの言葉を思い出して自分に言い聞かせています。

(DOG SCHOOL Visse)
2019年11月 7日 21:04





問題行動の主な原因は、経験不足とストレスです~ヴィッセのテキストから~
まずは、このことをしっかり理解して下さい。
無駄吠えや噛み付き、リードの引っ張りなど、個別の行動への対処は後回しにします。
その前に、
1.犬の生活環境を見直し整える。
2.ストレス解消を行う。
3.日常生活で行う3つのことを毎日実践する。
以上のことを理解して下さい。
これらのことは、今後、愛犬の問題行動を改善していくために、必要不可欠なことです。
とくに、1日8時間以上のお留守番をするワンちゃんを、
クレートやケージには、絶対に閉じ込めないで下さい。
ケージなどに長時間閉じ込めると、強いストレスがかかるので、問題行動がある犬には厳禁です。
犬自身が、自分では対処できないことと、何が起こるかわからないことは、ストレスの大きな原因になります。
ずっと閉じ込められていて自分では出られないというのは、人間でも非常に辛い状況です。
できれば、最低でも2畳位のスペースを確保して下さい。
そして、自分の意思で自由に動けるようにします。ただでさえ不安を抱えているところに、
その上、自分では出られない狭い場所に閉じ込められると、不安がますます募ります。
散歩は1日2回、最低40分~60分は連れて行って下さい。できれば、公園でロングリードをつけて
思いきり走らせてあげると最高です。散歩で気をつけることは、犬を好き勝手に歩かせないで下さい。
上記のことが改善されないと、無駄吠えや咬みつき、分離不安などは確実に悪化します。
もし、自分が愛犬と同じ生活環境に置かれたらどう感じるかを常に考えて下さい。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年7月16日 09:57





横浜市の犬のしつけ教室/問題行動の矯正法について
この行動療法の優れている点は、「客観性」と「明瞭性」で、技法自体が科学的で論理的であるので、体罰を与える暴力的なしつけを行うことは決してありません。しかし、行動療法だけですべての問題を解決できるものではないという事、そして、犬の心の奥底まで理解できるものではありません。
私も行動分析学を応用してレッスンを行ってはいますが、それ以上に「愛情」や「感情」の方を大切にしています。なぜなら、我々と同じように心を持つ生き物である犬には、机上の論理よりも時として愛情や感情の方が優るからです。
ですので、私は行動療法の他に、※補完代替療法として「アニマルコミュニケーション」と「アニマルヒーリング」を取り入れています。その理由として、問題行動の矯正は犬の心のリハビリと考えているからです。
問題行動で一番つらいのは犬自身なのです。※シーザー・ミランではありませんが、
「犬にはリハビリを」「飼い主には訓練を」が私のモットーです。問題行動は適切な生活環境を与え、
飼い主の方が犬の習性と学習の仕方を正しく理解できれば必ず改善します。
※シーザー・ミラン アメリカの有名なカリスマトレーナー。著書に「あなたの犬は幸せですか」がある。
※補完代替療法
補完代替療法とは、現代西洋医学以外の各種療法の総称。「相補する、補う」と「療法」を合わせた言葉で、一般的に自然療法や伝統的な医療を含めた様々な療法を指します。犬や猫の補完代替療法としては、ホメオパシーやバッチフラワーなどが代表的なものです。
補完代替療法では、表面に現れている身体的な問題だけではなく、精神的な状態やストレスの度合いなどの生活環境にも配慮し、犬の問題を部分的に捉えるのではなく、全体的(ホリスティック)に捉え、一頭一頭の症状に合わせて行うことが大きな特長です。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年7月15日 23:13





横浜市の犬のしつけ教室/無駄吠えなどの問題行動について
犬の行動は、飼い主との相互関係の中で発生している行動なので、飼い主が変化しなければ、犬の行動も変わりません。したがって、問題行動の矯正においては、犬の好ましくない行動だけを変えようとするのではなく、飼い主の行動と同時に意識も変えることが不可欠なのです。
その飼い主の行動と意識を変えるために必要なことは、
1.犬を毅然とした態度で叱れるようになること ☞叱れない親、叱れない上司
2.問題のみに目を向けるのではなく、犬との生活全般を見直すこと
3.問題を治すことが出来るのは、飼い主自身であるということ
以上の3つのことを理解して下さい。この3つのことを実践できなければ、
私がどんなに犬をトレーニングしても、問題の改善は見込めません。
1.の犬を毅然とした態度で叱ることは、散歩中に人や犬に吠えかかった時に、飼い主が何もリアクションをしなかったら、それは犬にとってその行為を、飼い主が肯定した=許したということになり、毎回同じ場面で吠えるようになります。
反対に飼い主が毅然とした態度で叱ることができれば、犬にとってその行為は、否定された=許されないということになります。ただし、叱り方が弱いと一緒に吠えている、または褒めてもらっていると思い、犬は肯定されたと勘違いします。
ただし、叱るだけでは吠えが治ることはありませんが、人や犬に向かって吠える行為、そして人を本気で咬む行為は、反道徳的行為です。それを絶対に許さないという、飼い主の毅然とした態度を犬に示すことが重要なのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年7月14日 17:27





横浜市の犬のしつけレッスン/お散歩の意味
犬は、どんな時に幸せを感じるのでしょうか?
みなさんは「犬の生きがいって何だろう?」と考えたことはありますか?
犬は好奇心のかたまりです。そして、狩猟動物である犬の好奇心は、探索する、追いかける、
破壊するという行動によって満たされます。ボールを追いかけるのは、獲物を追いかける本能であり、
ぬいぐるみの綿を取り出して破壊するのは、動物の内臓を引っ張り出す本能です。
警察犬や災害救助犬、麻薬探知犬たちが生き生きとして仕事をするのも、探索行動の探し当てた時の達成感から
得られる自分自身の喜びと同時に、飼い主の喜ぶ姿が犬にとっても幸せだからです。
では使役犬と違い、仕事を持たない無職の家庭犬にとって、幸せとは何でしょうか?
それは、大好きな飼い主とのお散歩です。
犬にとって、大好きな飼い主と共に行動する散歩の時間は、1日のうちで最も楽しい時間なのです。
散歩に行くことで外の世界と繋がり、五感が刺激され心と体を育むことができるのです。
毎日お散歩に行く犬の表情は、生き生きとしています。その反対に、あまりお散歩に連れて行ってもらえない子は、
外での刺激が不足し、神経質で臆病な子に育ちやすくなります。
とくに、長時間のお留守番をさせられて散歩が不足している犬は、不安やストレスをため込み、
精神的に不安定な状態で毎日を過ごしています。それが、無駄吠えや噛みつきという行動に現れるのです。
問題行動の多くは、長時間のお留守番と散歩不足によるストレスなのです。
私の生徒さんでペットショップの店員さんや獣医さんに、
「お散歩は毎日行かなくても、飼い主の都合で行けば大丈夫ですよ」と言われた方が何十人もいます。
言われた方のほとんどが、小型犬の飼い主の方々です。
これは多分、犬を「家畜」として「飼う」ことを前提に言われているのか、
「お散歩」と「運動」の違いを理解できていないかのどちらかだと思います。
家畜ということであれば、お散歩は飼い主の都合で行きたい時に行こうが、ケージに閉じ込めて、
お留守番を長時間させようが理解できます。しかし、「家族」として「共に暮らす」のであれば、
豊かな生活環境を与え、愛犬の心と体を健全に育むことが、飼い主としての義務であり、責任ではないでしょうか?
その一番の義務と責任がお散歩だと私は思っています。
愛情とは「言葉」ではなく「行動」です。
散歩は、愛犬の心と体を健全に育み、飼い主と信頼関係を築く基礎作りです。
散歩は、犬が犬としての喜びを感じる、1日で一番大切な時間です。
ヴィッセが考える犬のしつけとは、毎日朝・夕のお散歩が土台として成り立つものと考えています。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年5月 3日 10:25





横浜市の犬のしつけレッスン/犬を叱るということ~禁止のしつけ~
犬の学習は、
■行動を増やすか
■行動を減らすか
の2つになります。行動には、良い行動と悪い行動があります。
そして、犬のしつけには「スワレや」や「マテ」などの「動作を教えるしつけ」と、
犬が何か悪い行動をした時に、それをしてはいけないと教える「禁止のしつけ」のふたつがあります。
その悪い行動を減らそうとするために必ず使われるのが「罰」です。
罰とは、犬が何か好ましくない行動をした時に叱ったり、時には叩いたりして犬「嫌がること」や
「嫌がるもの」を使って、悪い行動をすると「嫌なことが起きるよ」と、学習させるために使われるものです。
犬が吠えた時に缶を投げて驚かしたり、無視するというのも罰ですが、
これらの方法を行っても、効果は全くありません。
罰は犬に痛みを与えたり、いうことを聞かせるために使うことが目的ではありません。
吠えることも含めて犬の行動を止めるために、一時的なブレーキとして使うものなのです。
ここでいう一時的なブレーキとは、「No!」や「ダメ!」「いけない!」と叱ることです。
しかし、善悪の概念と反省と後悔ができない犬を叱るだけでは、正しい行動を学習させることもできません。
罰はあくまでも、一時的なブレーキでしかないということです。
ただ、無駄吠えや飼い主を咬むなどの問題行動に対しては、それは本当にいけないことだと、
犬に伝わるまでしっかりと叱責する必要があります。☜ここが難しい
犬は、学習する生き物です。しかし、ほとんどの飼い主は、叱るだけで犬に学習する時間を与えません。
その学習とは、何回も何回も繰り返し、犬が正解にたどり着くまで根気強く教えなければならないのです。
ここまでの話で、犬を叱ってはいけないということではありません。
私も罰は使います。しかし、罰を使ったら必ず犬に正解を教え、褒めて終わります。
叱りっぱなしにしないで叱ることに責任を持ちます。
私が最も怖いのは、飼い主の罰を与える行動がエスカレートしていくことです。
ある生徒さんで、ラブラドールの雄が吠える度に、布団たたきで叩いて止めさせていた方がいました。
しかし、そのうち布団たたきでは効かなくなり、モップの柄で叩くようになりました。
モップの柄で効かなくなったら、次は金属バットになるのでしょう。
しかし、そうなる前にレッスンを受けてくれたので、もう叩くことなくその子の吠えは治りました。
犬に体罰を与えると、犬の反抗心を育ててしまうこともあります。もちろん、信頼関係は絶対に築けません。
さらに、いつも叱ってばかりいると※馴化してしまい、効果がなくなってしまいます。
「禁止のしつけ」の基本は、悪い行動を叱って減らそうとするのではなく、前述したとおり、
犬が正解を覚えるまで何回も何回も根気強く教え、良い行動を褒めて増やすことです。
そうして育てられた犬は、飼い主の望むことと、望まないことをきちんと理解できるようになるのです。
※馴化=何度もその刺激を受けているうちに、※刺激にだんだんと慣れてしまうこと。
※刺激=叱る、叩く、音、匂い、人、犬、車、オートバイ、触られる(ブラッシング・爪切り)物(掃除機など)
(DOG SCHOOL Visse)
2019年4月29日 10:54





横浜市の犬のしつけレッスン/無駄吠えについて
犬のしつけの問題行動の相談で、一番多いのが無駄吠えです。
犬が鎖に繋がれ庭で飼われていた昭和の時代に、無駄吠えという言葉はありませんでした。何故なら、吠えることで
番犬としての役割を果たしていたからです。庭で不審者に吠えて叱られる犬などいなかったことでしょう。
しかし、家族の一員として犬と一緒に暮らす時代になった今、番犬としての役割は終わり、
犬が吠える行為は、現在の家庭犬のしつけにおいて、最も困った問題行動として位置づけられようになりました。
「チャイムや音に反応して吠える」「気配を感じて吠える」「郵便屋さんや宅急便の人に吠える」など、
犬が吠えることには様々な理由があり、無駄に吠えているわけではありません。
また、毎日長時間のお留守番をさせられ散歩が不足している犬は、ストレスから慢性的に吠え続けることもありますが、これも理由があっての吠えです。そして、家の中での無駄吠えよりも相談が多いのが、散歩中の無駄吠えです。
散歩中に、自分の犬が他の犬に向かって吠えかかる時、相手に対して強気に吠えているようにも見えますが、
こうした他の犬や人に対して吠えて威嚇する犬たちに共通していることは、社会化不足だったり、
自分に自信がなく怖がりの犬ということです。
そして、散歩中の無駄吠えの背景には、犬自身が持つ恐怖心にあるのです。
「弱い犬ほど良く吠える」と、昔の人はよく言ったものです。
犬が通りすがりの他の犬や、人に吠えるようになるメカニズムを説明すると、以下のようになります。
① 向こうから犬が来た
↓
② 犬は自分の方へ近づいてきていると思っている
↓
③ すれ違いざまに吠えたら、相手はこちらに近づかずに通り過ぎた
↓
④ やったぁ! 追い払ったー!!
このように恐怖心を感じ、怖がった方の犬が「警戒吠え」をしたところ、相手の犬が近づかなかったので、
吠えかかった犬は「自分が追い払った」と勘違いをしているのです。相手はただ通り過ぎただけなのですが、
結果的に、怖がった犬は「警戒吠えをすれば、怖い犬は近づかない」と学習します。
これは、郵便配達の人や宅急便の人たちに吠えることも同じで、彼らは犬が吠えた後に必ず立ち去るので、
犬は自分が追い払ったと思っています。そして、毎回郵便屋さんや宅急便の人が来るたびに吠えて撃退し、
負け知らずの連戦連勝を重ねた犬は強気になり、吠えるという行動がますます強化されていきます。☞ 負の強化
さらに、もうひとつ厄介なことがあります。それは、自分の飼い主も一緒に守ろうとすることです。
この原因の多くは、飼い主が犬に対して取り続けた間違った対応にあります。
間違った対応とは、犬を自分より先に自由に歩かせ、犬の行きたい方について行くことです。
恐がりの犬を飼い主より先に歩かせてしまうと、歩哨(見張り)としての役割を遂行し、犬を発見すると
すぐにロックオンして相手が射程距離に近づくと一気に吠えかかってしまいます。☞ 縄張り性攻撃行動
もうひとつは、「お友達でしょー」とか「怖くないよー」など、優しい言葉をかけてしまうことです。
吠えている犬に優しい言葉は「ご褒美」となり、褒められていると勘違いした犬は、もっと吠えるようになります。
「オヤツで気を引く」というのもありますが、これは犬が吠えるたびにおやつという「ご褒美」を与えているので、
犬は「吠えればオヤツがもらえる」と学習し、これも効果はありません。
また、飼い主は叱っているつもりでも、犬にきちんと伝わらないと、犬は飼い主が一緒に吠えていると思い、
どんなに叱ってもまた同じ場面で吠えてしまいます。結局、吠える度に叱るという飼い主の行動も強化されていき、
一生叱り続けるという結果になってしまいます。☞ これも負の強化
犬が吠えた後に止めさせることが正解ではなく、すれ違う時に吠えないことが正解なのです。
では、散歩中の無駄吠えはどのように対処すればよいのでしょうか?
以下、まとめになります。
~まとめ~
1.犬とすれ違うときは、飼い主の前を歩かせずに、必ず犬を横につけて管理する。
2.犬とすれ違う際は、名前を呼んでアイコンタクトを取りながら歩く。
3.ベンチなどで休んでいて犬が近づいて来たときは、「待って」をかける。
4.日常生活で行う3つの事を実践する。
1. と 2.の犬とすれ違う時の最悪の対処は、犬を座らせて相手が通り過ぎるまで「待て」をさせることです。
間違いではありませんが、これは飼い主も犬もその度に緊張してしまい、散歩そのものが楽しくなくなります。
参考までに1~3の対処法を、「対立行動分化強化」と言います。
4.については、ヴィッセのレッスンを受講しないと分かりませんね?!
一応、企業秘密なのでここでは割愛させて頂きます。
いずれにしても、無駄吠えの矯正のポイントは、犬が吠えてから対処しようとするのではなく、
「常に先手を打って吠えさせないこと」につきます。後手に回ると、スイッチを切ることがとても難しくなります。
前述した3つの強化法を繰り返し学習させ、自分の犬に吠える機会を与えない様に、根気よく犬に学習をさせれば、
無駄吠えは必ず改善します。犬の無駄吠えが改善するかどうかは、飼い主次第なのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年4月26日 21:16





横浜市の犬のしつけレッスン/人生に遅すぎるということはない。
~2017年8月3日のブログから~
先日、万葉の湯の帰りにカップヌードルミュージアムの前を通ったら、いろいろな言葉がタイルに埋め込まれていました。その中でもっとも気に入った言葉がこれです。テニスコーチになりたくて、テニスを始めたのが23歳の時、ドッグトレーナーになりたくて訓練所で勉強をはじめたのが41歳の時。
そして、絵本の世界を通して犬のしつけを世の中に広めたいと思い、※絵本作家になりたくて絵本の勉強をはじめたのが59歳の時。気がつけば還暦を迎えてしまった。まだまだ絵本作家になれたとは言えないが、残り20年?! これからもこの言葉を胸に刻んで生きていきたい。
※「家族を愛するすべての大人へ」に次ぐ2作目、「世界一だいすきなあなたへ」の動画ができました。トップページからご覧下さい。
![IMG_6191-thumb-500x375-2788[1]-thumb-500x375-3331[1].jpg](http://www.visse.co.jp/blog/assets_c/2018/12/IMG_6191-thumb-500x375-2788%5B1%5D-thumb-500x375-3331%5B1%5D-thumb-500x375-3435.jpg)
(DOG SCHOOL Visse)
2018年12月12日 16:44





<<前のページへ|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|次のページへ>>
« ただいまお勉強中! | メインページ | アーカイブ | ご案内 »