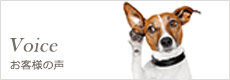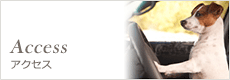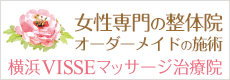月別 アーカイブ
- 2025年4月 (3)
- 2025年3月 (24)
- 2025年2月 (23)
- 2025年1月 (24)
- 2024年12月 (26)
- 2024年11月 (28)
- 2024年10月 (30)
- 2024年9月 (28)
- 2024年8月 (19)
- 2024年7月 (27)
- 2024年6月 (28)
- 2024年5月 (26)
- 2024年4月 (21)
- 2024年3月 (26)
- 2024年2月 (24)
- 2024年1月 (21)
- 2023年12月 (24)
- 2023年11月 (24)
- 2023年10月 (23)
- 2023年9月 (23)
- 2023年8月 (17)
- 2023年7月 (26)
- 2023年6月 (14)
- 2023年5月 (22)
- 2023年4月 (26)
- 2023年3月 (24)
- 2023年2月 (26)
- 2023年1月 (19)
- 2022年12月 (23)
- 2022年11月 (22)
- 2022年10月 (21)
- 2022年9月 (15)
- 2022年8月 (18)
- 2022年7月 (23)
- 2022年6月 (26)
- 2022年5月 (21)
- 2022年4月 (18)
- 2022年3月 (25)
- 2022年2月 (22)
- 2022年1月 (20)
- 2021年12月 (26)
- 2021年11月 (27)
- 2021年10月 (23)
- 2021年9月 (20)
- 2021年8月 (13)
- 2021年7月 (20)
- 2021年6月 (20)
- 2021年5月 (19)
- 2021年4月 (25)
- 2021年3月 (27)
- 2021年2月 (21)
- 2021年1月 (19)
- 2020年12月 (23)
- 2020年11月 (28)
- 2020年10月 (22)
- 2020年9月 (18)
- 2020年8月 (20)
- 2020年7月 (25)
- 2020年6月 (24)
- 2020年5月 (18)
- 2020年4月 (19)
- 2020年3月 (21)
- 2020年2月 (18)
- 2020年1月 (16)
- 2019年12月 (25)
- 2019年11月 (21)
- 2019年10月 (25)
- 2019年9月 (24)
- 2019年8月 (16)
- 2019年7月 (26)
- 2019年6月 (29)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (14)
- 2019年3月 (20)
- 2019年2月 (16)
- 2019年1月 (15)
- 2018年12月 (15)
- 2018年11月 (18)
- 2018年10月 (17)
- 2018年9月 (17)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (18)
- 2018年6月 (15)
- 2018年5月 (15)
- 2018年4月 (20)
- 2018年3月 (22)
- 2018年2月 (15)
- 2018年1月 (16)
- 2017年12月 (18)
- 2017年11月 (18)
- 2017年10月 (13)
- 2017年9月 (21)
- 2017年8月 (17)
- 2017年7月 (17)
- 2017年6月 (13)
- 2017年5月 (12)
- 2017年4月 (16)
- 2017年3月 (16)
- 2017年2月 (10)
- 2017年1月 (11)
- 2016年12月 (14)
- 2016年11月 (12)
- 2016年10月 (12)
- 2016年9月 (12)
- 2016年8月 (12)
- 2016年7月 (13)
- 2016年6月 (18)
- 2016年5月 (19)
- 2016年4月 (19)
- 2016年3月 (13)
- 2016年2月 (15)
- 2016年1月 (16)
- 2015年12月 (16)
- 2015年11月 (13)
- 2015年10月 (16)
- 2015年9月 (14)
- 2015年8月 (13)
- 2015年7月 (13)
- 2015年6月 (15)
- 2015年5月 (19)
- 2015年4月 (23)
- 2015年3月 (15)
- 2015年2月 (15)
- 2015年1月 (13)
- 2014年12月 (12)
- 2014年11月 (10)
- 2014年10月 (9)
- 2014年9月 (18)
- 2014年8月 (9)
- 2014年7月 (12)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (12)
- 2014年4月 (16)
- 2014年3月 (12)
- 2014年2月 (8)
- 2014年1月 (5)
- 2013年12月 (8)
- 2013年11月 (7)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (7)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (3)
- 2013年6月 (5)
- 2013年5月 (6)
- 2013年4月 (5)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (6)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (1)
- 2012年10月 (4)
- 2012年9月 (1)
- 2012年2月 (1)
- 2012年1月 (1)
- 2011年12月 (1)
- 2011年11月 (1)
- 2011年7月 (1)
- 2011年5月 (2)
- 2011年4月 (1)
- 2011年1月 (2)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (2)
- 2010年9月 (2)
- 2010年8月 (1)
- 2010年7月 (4)
- 2010年6月 (2)
- 2010年5月 (1)
最近のエントリー

HOME > Visse's Blog > アーカイブ > エッセイの最近のブログ記事
Visse's Blog エッセイの最近のブログ記事
横浜市の犬のしつけ教室/犬を理解しましょう~ヴィッセのテキストから~
犬は人の言葉を音声として認識します。短い動詞や名詞は理解できますが、「そっち行っちゃだめ」とか「ちゃんと前向いて歩きなさい」など、人間の子供のように話しかけても理解できません。これは英語が理解できない人に、いくら話しかけても理解してもらえないのと同じことです。
2.反省と後悔ができない
人間のように「思考」することのない犬は、「反省」と「後悔」ができません。何が悪いのかの理由づけが出来ない犬を叱るだけでは、良い行動は増えません。例えば、飛びつく犬に「ノー!」と叱るだけでは飛びつきは治りません。
3.犬に期待しすぎない、すぐに結果を求めないこと
習い事は、人も犬もすぐには上達しません。また、人間にとっての当たり前が、犬にとっては、当たり前ではないということを忘れないで下さい。
4.犬の行動は固定的ではなく、良い方にも悪い方にも常に変化している
犬の学習の仕方は、「上書き学習」。常に新しい学習をしています。犬の行動が良くも悪くもなるのは、飼い主次第です。訓練所に預けて帰ってきたら元に戻ったという話をよく聞きますが、犬を預けている間、飼い主は何も成長していないので当たり前の話です。
5.犬に厳しくするのではなく、自分に厳しくすること
犬に理想や完璧を求めるなら、自分がそうであるかどうかを自問する。完璧な飼い主にはなれそうにないと思ったら、犬にも完璧を求めない。
6.馬鹿な犬はいない
犬を馬鹿呼ばわりしている飼い主は、犬を叱るだけで適切な学習を与えない飼い主です。
7.身の回りのものは人の手も含め、すべて噛むためのオモチャだと認識している
ものを鑑賞するという趣味はない⇒破壊するのが大好き。
8.道徳心と価値観を持たない(善・悪の概念がない)
飼い主の価値観と、道徳心がそのまま犬に反映する。犬のしつけは飼い主次第。
(DOG SCHOOL Visse)
2021年4月12日 08:49





横浜市の犬のしつけ教室/罰について~ヴィッセのテキストから~
今日、以下のようなお問い合わせがありました。内容は略してあります。
警戒心が強く生活音に吠えます。
チャイム、掃除機、キッチンの引き出しやグリルの開け閉め、モップやクイックルワイパー、サランラップやアルミホイルを切る音等、散歩時はバイクや自転車、買い物時は買い物カートやベビーカー等です。
警察犬訓練士の方に、犬が吠えたら新聞紙を丸めた物を床に叩きつけてびっくりさせる事を勧められて実行しました。最初は静かになったのですが、数回やるうちに慣れてきたのか攻撃的になり、新聞紙に襲いかかってくる様になりました。それ以来、やめました。その頃からも吠えがひどくなったと思います。
今後、どの様にしていったら良いでしょうか? 宜しくお願い致します。
犬が吠えた時や、何か良くない行動をした時に
・叱る ・叩く ・無視する ・マズルをつかむ ・音の出る缶を投げ驚かす
・吠えると電流が流れる首輪をつける ・お酢を水で薄めてスプレーをかける
・仰向けにして押さえつける ・リードを強く引っ張り首にショックを与える
などの対処の仕方がありますが、上記の事項を行動分析学で「罰」と呼んでいます。
これらの対処法は、犬を「家畜」として扱うことを前提としたしつけの方法です。
そして、犬の悪い行動を減らそうとするために必ず使われるのが、「罰」です。罰と言うのは、犬が好ましくない行動をした時に、叱ったり、時には叩いたりして犬の「嫌がること」や、「嫌がるもの」を使って、その行動をすると「嫌なことが起きるよ」と学習させるために使われるものです。ちなみに「嫌悪刺激」と呼んでいます。
犬が吠えた時に、缶を投げて驚かしたり、無視するというのも罰です。(まったく効果はありませんが…。)
☝の新聞紙を丸めて床に叩きつけて脅かすというのも古典的な罰です。同じく全く効果はありません。
もし、仮に効果があったとしても私が最も怖いのは、飼い主の「罰を与える行動がエスカレートしていく」ことです。
罰は犬に痛みを与えたり、いうことを聞かせるために使うことが目的ではありません。ただ、行動を止めるための一時的なブレーキとして使うのです。言い換えれば、罰は一時的なブレーキでしかないということです。
善悪の概念と反省と後悔ができない犬に、罰を与えるだけでは犬に正しい行動を学習させることはできません。
犬は、学習する生き物です。しかし、ほとんどの飼い主は、叱るだけで犬に学習する時間を与えようとしません。
ここまでの話で、犬を叱ってはいけないということではありません。私も罰は使います。しかし、罰を使ったら必ず犬に正解を教え、褒めて終わります。叱りっぱなしにしないで、叱ることに責任を持ちます。
そして、罰を与えるだけのしつけ方は、☝の方の犬のように犬の反抗心を育ててしまうこともあります。さらに、罰は与えるうちに※馴化してしまい、効果がなくなってしまいます。もちろん、信頼関係は絶対に築けません。
しつけの基本は、叱って教えようとするのではなく、とくに「禁止のしつけ」では、犬が正解を覚えるまで何回も何回も、根気強く教え学習させることです。そうして育てられた犬は、飼い主の望むこと、望まないことを、きちんと理解できるようになるのです。
いまだに☝のようなしつけ方が行われていることに、驚きと失望を覚えるばかりです。
※馴化=何度もその刺激を受けると、その刺激に慣れてしまうこと。
(DOG SCHOOL Visse)
2020年7月15日 14:07





横浜市の犬のしつけ教室/無駄吠えについて~ヴィッセのテキストから~
犬のしつけの問題行動の相談で、一番多いのが無駄吠えです。犬が鎖に繋がれ庭で飼われていた昭和の時代に、無駄吠えという言葉はありませんでした。何故なら、吠えることで番犬としての役割を果たしていたからです。庭で不審者に吠えて叱られる犬などいなかったことでしょう。
しかし、家族の一員として犬と一緒に暮らす時代になった今、番犬としての役割は終わり、犬が吠える行為は、最も困った問題行動として位置づけられようになりました。
「チャイムや音に反応して吠える」「気配を感じて吠える」「郵便屋さんや宅急便の人に吠える」など、犬が吠えることには様々な理由があり、無駄に吠えているわけではありません。
そして、家の中での無駄吠えよりも相談が多いのが、散歩中の無駄吠えです。
散歩中に、自分の犬が他の犬に向かって吠えかかる時、相手に対して強気に吠えているようにも見えますが、こうした他の犬や人に対して吠えて威嚇する犬たちに共通していることは、社会化不足だったり、自分に自信がなく怖がりの犬ということです。
そして、散歩中の無駄吠えの背景には、犬自身が持つ恐怖心にあるのです。
「弱い犬ほど良く吠える」と、昔の人はよく言ったものです。
犬が通りすがりの他の犬や、人に吠えるようになるメカニズムを説明すると、
以下のようになります。
① 向こうから犬が来た
② 犬は自分の方へ近づいてきていると思っている
③ すれ違いざまに吠えたら、相手はこちらに近づかずに通り過ぎた
④ やったぁ! 追い払ったー!!
このように恐怖心を感じ、怖がった方の犬が「警戒吠え」をしたところ、相手の犬が近づかなかったので、吠えかかった犬は「自分が追い払った」と勘違いをしているのです。相手はただ通り過ぎただけなのですが、結果的に、怖がった犬は「警戒吠えをすれば、怖い犬は近づかない」と学習します。
これは、郵便配達の人や宅急便の人たちに吠えることも同じで、彼らは犬が吠えた後に必ず立ち去るので、犬は自分が追い払ったと思っています。そして、毎回郵便屋さんや宅急便の人が来るたびに吠えて撃退し、負け知らずの連戦連勝を重ねた犬は強気になり、吠えるという行動がますます強化されていきます。☜負の強化
さらに、もうひとつ厄介なことがあります。それは、自分の飼い主も一緒に守ろうとすることです。この原因の多くは、飼い主が犬に対して取り続けた間違った対応にあります。
間違った対応とは、犬を自分より先に自由に歩かせ、犬の行きたい方について行くことです。恐がりの犬を飼い主より先に歩かせてしまうと、見張り役としての役割を忠実に遂行して犬を発見するとすぐにロックオンし、相手が射程距離に近づくと一気に吠えかかってしまいます。ちなみに、縄張り性攻撃行動と言います。
もうひとつは、「お友達でしょー」とか「怖くないよー」など、優しい言葉をかけてしまうことです。吠えている犬にやさしい言葉は「ご褒美」となり、褒められていると勘違いした犬は、もっと吠えるようになります。「オヤツで気を引く」というのもありますが、これは犬が吠えるたびにおやつという「ご褒美」を与えているので、犬は「吠えればオヤツがもらえる」と学習し、これも効果はありません。
また、飼い主は叱っているつもりでも、犬にきちんと伝わらないと犬は飼い主が一緒に吠えていると思い、どんなに叱ってもまた同じ場面で吠えてしまいます。結局、吠えるたびに叱るという飼い主の行動も強化されていき、一生叱り続けるという結果になってしまいます。☜これも負の強化
では、散歩中の無駄吠えはどのように対処すればよいのでしょうか?
以下、まとめになります。
~まとめ~
1.犬とすれ違うときは、飼い主の前を歩かせずに、必ず犬を横につけて管理する。
2.犬とすれ違う際は、名前を呼んでアイコンタクトを取りながら歩く。
3.ベンチなどで休んでいて犬が近づいて来たときは、「待って」をかける。
4.日常生活で行う3つの事を実践する。
1. と 2.の犬とすれ違う時の最悪の対処は、犬を座らせて相手が通り過ぎるまで「待て」をさせることです。間違いではありませんが、これは飼い主も犬もその度に緊張してしまい、散歩そのものが楽しくなくなります。参考までに1~3の対処法を、「対立行動分化強化」と言います。
4.については、ヴィッセの出張レッスンを受講しないと分かりませんね?!
一応、企業秘密なのでここでは割愛させて頂きます。
いずれにしても、無駄吠えの矯正のポイントは、犬が吠えてから対処しようとするのではなく、「常に先手を打って吠えさせないこと」につきます。後手に回るとスイッチを切ることが、とても難しくなります。
前述した3つの強化法を繰り返し学習させ、自分の犬に吠える機会を与えない様に根気よく犬に学習をさせれば、無駄吠えは必ず改善します。そして、犬の無駄吠えが改善するかどうかも、やはり飼い主次第なのです。
(DOG SCHOOL Visse)
2020年7月 8日 13:09





横浜市の犬のしつけ教室/犬を叱るということ~ヴィッセのテキストから~
■行動を増やすか
■行動を減らすか
の2つになります。行動には、良い行動と悪い行動があります。
そして、犬の悪い行動を減らそうとするために必ず使われるのが、「罰」です。
罰と言うのは、犬が好ましくない行動をした時に、叱ったり、時には叩いたりして犬の「嫌がること」や、
「嫌がるもの」を使って、その行動をすると「嫌なことが起きるよ」と学習させるために使われるものです。
犬が吠えた時に、缶を投げて驚かしたり無視するというのも罰です。(まったく効果はありませんが…。)
しかし、罰は犬に痛みを与えたり、いうことを聞かせるために使うことが目的ではありません。
ただ、行動を止めるための一時的なブレーキとして使うのです。
言い換えれば、罰は一時的なブレーキでしかないということです。
ただ、無駄吠えや飼い主を咬むなどの問題行動に対しては、それは本当にいけないことだと
犬に伝わるまでしっかりと叱責する必要があります。
善悪の概念と反省と後悔ができない犬に、罰だけでは犬に正しい行動を学習させることはできません。
犬は、学習する生き物です。しかし、ほとんどの飼い主は、叱るだけで犬に学習する時間を与えません。
ここまでの話で、犬を叱ってはいけないということではありません。
私も罰は使います。しかし、罰を使ったら必ず犬に正解を教え、褒めて終わります。
叱りっぱなしにしないで、叱ることに責任を持ちます。
罰で私が最も怖いのは、飼い主の「罰を与える行動がエスカレートしていく」ことです。☜ 負の強化
そして、時には犬の反抗心を育ててしまうこともあります。さらに、いつも叱ってばかりいると、
※馴化してしまい、効果がなくなってしまうことです。もちろん、信頼関係は絶対に築けません。
しつけの基本は、叱って教えようとするのではなく、とくに「禁止のしつけ」では、
犬が正解を覚えるまで何回も何回も、根気強く教え学習させることです。
そうして育てられた犬は、飼い主の望むこと、望まないことを、きちんと理解できるようになるのです。
※馴化=何度もその刺激を受けると、その刺激に慣れてしまうこと。
(DOG SCHOOL Visse)
2020年5月14日 18:26





落ち着かない犬とは?~ヴィッセのテキストから~
「この子は落ち着きがなくて」と言う飼い主は少なくありません。
落ち着きがない犬とは、どういう犬なのでしょうか?
落ち着きがない犬とは、「自分の感情と行動をコントロールできない犬」のことです。
タイプとしては、活発過ぎる子に多く見られ、「我慢」する能力を持ち合わせていません。
よく4~5ヶ月齢の子犬に「この子は落ち着きがなくて」と言われる飼い主が多いのですが、
4~5ヶ月の子犬は、自分で感情と行動をコントロールすることはできません。
なぜなら、相手はまだ脳みそが固まっていない、エネルギーの塊のような赤ちゃんだからです。
もし、1才を過ぎて成犬になっても落ち着きがなければ、
それは、「飼い主が犬に我慢することを教えられなかった」と言えるでしょう。
1年後、2年後の愛犬の姿は、飼い主が育てた結果の姿なのです。
ヴィッセが考える犬のしつけとは、
犬に「衝動の抑制と感情のコントロール=我慢」を、教えることが中心となります。
そして、その基礎となるのが、「コントロールポジション」と「境界線トレーニング」です。
コントロールポジションは、活発なワンちゃんはもちろん、とくに怖がりのワンちゃんや、
甘えん坊のワンちゃんを情緒の安定した犬に育てるには、家の中だけではなく、
外のどんな場所でも出来るようにならなければなりません。
なぜなら、これらの犬は、飼い主の膝の上が最も安全な場所なので、いつも抱っこをせがみます。
その結果、飼い主がつい抱っこをしてしまいがちです。そうするといつまでたっても、
「衝動の抑制と感情のコントロール」の効かない、我慢が出来ない犬になってしまいます。
コントロールポジション中に犬が抱っこをせがむ場合は、犬が諦めるまで「無視」するか、
毅然と叱って「拒否」することです。注意することは、絶対に目を合わせない事と、
中途半端に叱らないことです。もちろん触ってもいけません。
境界線トレーニングは、犬が大興奮してもっとも衝動的になる時に行います。
クレートから出してもらえる時、ごはんの時、首輪とリードを付ける時、お散歩で玄関を出る時、
お友達に出会った時などです。※日々実践してください①を参照
(DOG SCHOOL Visse)
2020年2月27日 11:40





横浜市の犬のしつけ教室/犬のしつけは飼い主次第~ヴィッセのテキストから~
「訓練所に預けたけど、帰ったら元に戻った」 「本を何冊も読んだけど、上手くいかなかった」
「しつけ教室に通ったが、トレーナーの言うことは聞くけど、私のいうことは聞かない」」など、
こういう話をよく耳にします。
何故こういうことが起きるのかというと、↑ の方々に共通していることは、
「何のためにしつけをするのか?」という目的(ゴール)がないまま、
しつけやトレーニングを行っているからだと思います。
別なことで例えれば、「英会話教室に通ったけど全然喋れるようにならなかった」と言われる方も、
そこに目的や必要性がないからです。しつけの目的は、それぞれの飼い主によって違うと思います。
「自分が不安だから」 「周りに迷惑をかけないため」 「快適に暮らす為」など・・・。
そして、その答えは、貴方自身が自分で考えて出さなければならない答えなのです。
他人に聞いても答えられない問題なのです。なぜなら愛犬と暮らしているのはあなたであり、
あなたの生活も犬も、他の方とは全く違うからです。
僕も日中、犬を預かってレッスンをするので、「犬を預けると先生のいうことは聞いても、
飼い主のいうことは聞かないのではないでしょうか?」という質問はよく受けます。
以前、ご夫婦で問題行動のカウンセリングを受けられた奥様から、同じ質問を受けました。
すると、傍にいたご主人がすかさず、「もしそうなったら、俺たちが駄目だってことだよ」と、
奥様に言ってくれたのです。僕は思わずご主人に拍手をしてしまいました。
しつけ教室は「基礎」を学ぶところです。私がどんなに犬をトレーニングしても、飼い主が
トレーナーから学んだことを、日常生活という「応用」の場で「実践」できなければどうにもなりません
そして、自分が愛犬になったつもりで、「自分の生きがいは何だろう?」ということも考えてみて下さい。
「ご飯を食べること」 「散歩に行くこと」 「ボールを追いかけること」 「友達に会うこと」
なんだか禅問答のようになってしまいましたが、これらの疑問に対する答えはひとつではありません。
何故なら100の家庭があれば、100通りの暮らし方があるのですから。
そして、その答え一つひとつをじっくりと探してみてください。
※ちなみに私の答えは、「誰からも愛され、どこに出しても恥ずかしくない子に育てる為」です。
(私)今日も楽しかったね! (大ちゃん)はい!!

(DOG SCHOOL Visse)
2020年2月20日 17:42





横浜市の犬のしつけ教室/犬と暮らすということ~ヴィッセのテキストから~
犬は、飼い主の態度や姿勢を常に見ています。
その姿勢や態度が、犬が飼い主を主人だと判断する基準になります。
さらに、飼い主の価値観と道徳観はそのまま犬に反映します。
犬の行動は、飼い主の性格と与える環境で大きく変わるのです。
今、巷に存在する「しつけ」の方法をどんなに実践しても、
そこに、しつけの意味と目的を見出せなければ、上手く行くことはありません。
また、おやつを使うだけのインスタントなしつけをしても、犬と心がつながることはないでしょう。
親と子、先生と生徒、上司と部下、飼い主と犬、これらの関係はみんな尊敬で成り立ちます。
以前、散歩の時に見かけた光景があります。
ホームレスの方が、自転車の荷台に目一杯の空き缶を積んで歩いていました。
その横を一頭の犬がぴったりと側について歩いています。
その犬は、好き勝手に匂いを嗅ぐことも、引っ張ることもありませんでした。
そして、お互いが助け合うように寄り添っていた姿に、犬と暮らす本質を教えられた気がします。
子供のしつけに近道なんてないように、犬のしつけにも近道はありません。
古くは古代から、イヌはヒトと暮らしてきました。ワニと、その歯の掃除をする小鳥みたいに。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月23日 09:56





横浜市の犬のしつけ教室/ヴィッセの基本理念~ヴィッセのテキストから~
■ヴィッセの基本理念
目標:心と体を育み、情緒が安定した誰からも愛される犬に育てること。
まず愛犬の気持ち、感情を理解して相手を尊重することから始めます。
「スワレ」や「マテ」などを教える時に、きつい言葉や命令調で指示をしたりしません。
強制して言うことを聞かせようとすることは、犬との「絆」を壊します。
ヴィッセでは、「すわって」「まって」「おいで」「行こう」と、
子供に語りかけるように言っています。ここでいう子供とは、幼稚園児以下だと思って下さい。
逆に、たとえやさしい言葉であっても、オヤツを使っていても、
嫌がっていることをやらせれば、それは強制であり犬にとってはやさしくありません。
愛犬の声に耳を傾け、気持ちを理解し、
双方向のコミュニケーションを築くことが基礎になります。
また、甘噛みをしたら「マズルをつかんで叱る」「口の中に手を入れて叱る」などの
暴力的な行為は絶対に行いません。
■スワレやマテなどを、いちいち指示でさせません。
これらの動作は、犬がパニックになったり、興奮して衝動と感情をコントロール
できなくなった時以外は、イヌが自分で判断して自発的に行う事と考えています。
また、食餌の時、床にご飯を置いてマテをさせたり、「スワレ~マテ」を教えるときに、
おやつを見せて教える人がいますが、これは、食べ物に対する執着心を生み、
無駄なストレスをかけるので、行わないで下さい。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月22日 21:12





横浜市の犬のしつけ教室/人と犬の動かし方~ヴィッセのテキストから~
■犬がいうことを聞いてくれるようになるには~ヒトとイヌの動かし方~
●脅す=体罰などで恐怖心を与える
→従う犬(人間)もいる
→反発する犬(人間)もいる
●懇願する=犬に気を遣う
→頼りなく感じる
→リーダーとしては認めてくれない
●金や物でつる=オヤツやオモチャ
→それだけの関係
→もらう時しかいうことを聞かない
●尊敬される=犬に楽しく学習させる
→犬の心を掴む
→犬が希求的にいうことを聞いてくれる
※人も犬も、妻も子供も、部下も業者さんも気持ちよく動かすことが理想。
そして、動物の行動は、すべてモチベーション。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月21日 18:53





横浜市の犬のしつけレッスン/犬の学習の仕方~ヴィッセのテキストから~
私たち人間の反応によって、行動が強化されるからです。
犬は、自分の利益になることはすぐに学習すると同時に、
飼い主が喜ぶことは自分も嬉しくなり、何度でも繰り返したくなります。
例えば首輪やリードを付ける時に、「待って、待って!落ち着いて、ほら動かないで!!」と、
飼い主が話しかけすぎると、犬は飼い主が喜んでいると思い、余計に興奮するようになります。
飼い主が喜んでいることに気づいた犬は、飼い主を喜ばせるには
「じっとしていないことが良いことだ」ということを学んでいるのです。
犬に大人しく首輪やリードを付けさせるには、話しかけすぎないことです。
しかし、これは女性にとって難しいことのようです。犬にリードを付ける度に
飼い主が話しかけすぎるのは、犬の方が飼い主を訓練したとも言えるでしょう。
このように飼い主の知らないところで、お互いを訓練し合っているのです。
しかし、どちらかと言えば、飼い主が犬に訓練されていることの方が多いようです。
分かりやすい例として「飛びつき」があります。
犬が飛びついた時に、飼い主がなだめるように叱ると、犬にとって飼い主の言葉が「ご褒美」となり、
犬は飼い主が喜んでいると思い、余計に飛びつくようになってしまいます。
犬の飛びつきが直らないのは、飼い主が毅然と拒否していないからなのです。
こうして飼い主は叱っているつもりでも、犬にとっては「ご褒美」となっていることは
様々な場面で見受けられます。犬は、物事を「利益=快」「不利益=不快」で判断します。
自分に都合が良いことはすぐに学習しますし、逆に飼い主にとって都合が悪いことは、
なかなか覚えてくれません。飼い主の方は、自分の与えている言動が犬にとって
「ご褒美」となっていないかを、常に意識するようにしましょう。
(DOG SCHOOL Visse)
2019年12月12日 18:30





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>
« ただいまお勉強中! | メインページ | アーカイブ | ご案内 »